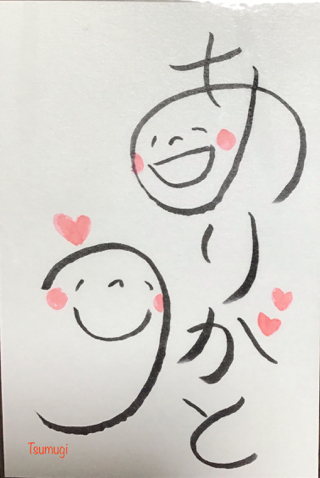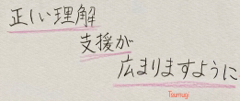こちらまでお越しいただきありがとうございます。
第5回 かんもくフォーラム オンライン企画が終了しました。
YouTube Liveでの生配信。
全国のいろんな方と繋がり学べたこと嬉しく思います。
私は子どもと拝見させていただきました。
今回は、場面緘黙入門。
短時間でギュッと内容が詰まっていて、分かりやすく、たくさんのことを学ばせていただきました。
本番は45分ですが、この日のためにご自身の貴重な時間を費やして素敵な講演にして下さった高木先生。
企画、運営実行委員の皆様、香梅さん、そんな皆様を支え見守って下さるご家族の皆様。
お1人おひとりのおかげです。
ありがとうございました。
来年度は、北海道で開催予定とのこと。
いつか、開催地で皆さんと直接交流したい!です。
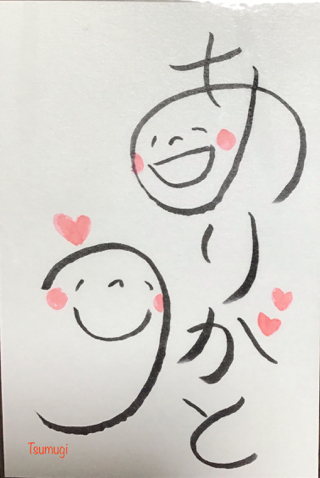
1人の声、力では聞いてもらえないことも、
みんなでチカラを合わせて動いて行けば大きなものになります。
一緒に動いてみませんか。
声を届けていきませんか。
動かなければ何も始まらない。
動くことで回り出す。
バラバラに動くよりも、
みんなで団結していけるとより心強いですし、届きやすくなります。
聞いてもらえない
分かってもらえない
専門家がいない
ない、ない、ないもの探しではなくて、それなら何ができるかな。
今のこの状況では何ができるかな。
できることを探してみる。
やり方、考え方を変えてみる。
素敵なことですね!
やり方や考え方を変えてみると、新しい発見もある。
これは、生活そのものにも活かせますね。
みんなでチカラを合わせていきましょう。
でも、今は動けないと思う時は無理をしなくてもいいと思います。
自分自身の心身のエネルギーが充分でないのに動くなんて、しんどいですよね。
動けない自分を責めるのではなくて、今まで頑張ってきた自分を充分に休ませてあげることも大切。
自身の心身のエネルギーをしっかり蓄えることってとっても大切です。
少し動けそうになった時に自分のペースでいいので、
自分の心動くもの、やってみたいことをしてみるのもいいかもしれません。
少し動いてみると違う景色が見えてくることもあります。
もしも、今までと何も変わらないと思ったとしても、あなたが勇気を出して踏み出した一歩で、自分では気づかないものが、もう動き出しています。
自分を褒めて下さい。
親を助けてくれる存在も必要。
子どもを助けてくれる存在も必要。
共に歩いて行ってくださる方がいると心強いですし、嬉しいです。
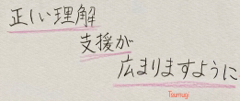
場面緘黙は、子ども、親だけで改善されるものではありません。
問題は学校の外だけにあるわけではありません。
内の環境(学校の中)にも目を向けてみませんか。
子どもたちが1日の大半を過ごしている学校。
そこにいる先生方の関わり方もよく考えていただけるだけで、環境が少しでも変わるのではないかなぁと思います。
日々子どもたちに接している先生(親)の言葉遣い、態度。
大きな声で子どもたちを動かしてないだろうか。
子どもたちに恐怖を植えつけてないだろうか。
不安を与えていないだろうか。
言葉や態度で子どもたちを傷つけてはいないだろうか。
子どもたちを萎縮させてはいないだろうか。
大人が偉いんじゃない。
大人は子どもよりも上じゃない。
子どもは教室、学校で安心は得られているのだろうか。
(家庭も一緒です)
子どもや家庭(外側)だけに問題を投げかけても何も始まりません。
何も学べません。
自分の内側も見てみませんか。
みんなで一緒に考えていきませんか。
悩み苦しんでいる子どもたち(人)、寂しい瞳をしている子どもたち(人)
そういう子どもたち(人)のところに心を寄せて。
安心できる環境ってなんだろう。
安心できる人ってどういう人だろう。
自分を安心して出せる状況ってどんなのだろう。
ありのままでいていい場所ってどんなところだろう。
相手の歩みに合わせるってどういうことだろう。
注)このブログは何かや誰かを批判するものではありません。
かんもくフォーラムの内容とは一切関係はありません。
物事を通して、共に考え、子どもたちが安心して過ごせる人的環境を整えていきたいです。

正しく知ってほしいこと。
以下、高木先生の講演より。
話せないという氷山の下には、
子どもの持っている要素
+ 本人の外側にある問題があります。
【本人の持っている要素】
・抑制的な気質(不安や緊張を感じやすい)
・感覚的な過敏さ
・他の不安症や発達障がい
・言語能力や知的能力の問題
【外側にある問題】
・不安や緊張を感じやすい環境
・本人にとって過剰な負担になる刺激や課題
・話す相手の問題(先生やクラスメイトの態度や様子)
・不適切な対応、放置
【医学的には】不安症(不安障害)のグループに分類
【法令上】発達障害者支援法第二条で定義される発達障がいに該当
【学校教育】特別支援教育の対象として、情緒障害に分類
場面緘黙は適切な介入により症状を改善させることができる
〜終わり〜
『大げさ』『考えすぎじゃないの』『みんなは大丈夫なのに』『みんな平気なのに』ではなく、
感覚的なもの感じ方は人それぞれ、
その子ども(人)自身がどのように感じているのかが大切であり、そこを受け止め理解していく必要があるのかなと思います。
子どものステップで、子ども主体に。
焦らず、ゆっくり。子どもの歩みに合わせる。
小さな大丈夫を積み重ねて。
できた!という経験を大切に。
大丈夫、できた、やった!という経験こそ、その子自身の大きなチカラになります。

場面緘黙関連の書籍もたくさん出ています。
かんもくネット書籍案内
購入される方は、かんもくネット書籍案内からご購入いただけると嬉しいです。
場面緘黙・吃音の正しい理解が広がりますように。
子どもたち、当事者、経験者。家族。
全ての方々が安心して歩いて行ける学校、地域、社会となりますように。
孤独で苦しみの中にいるあなたのもとにこの声が届きますように。
あなたは決して1人じゃないよ。
あなたは大切な存在。
居てくれてありがとう。
出会ってくれてありがとう。
暗闇の中にあたたかな光が射す日は必ずくるから。
一緒に歩いて行こうよ。
最後までお読みいただきありがとうございました。